
院長コラム
講演報告:「SGLT2阻害薬を読み解く、循環器内科医の立場から」
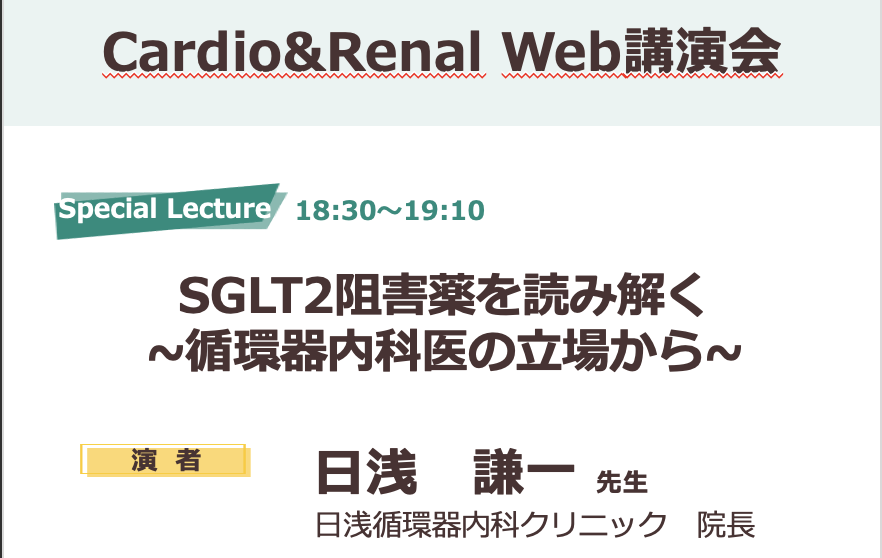
先日、医師や医療関係者向けに
「SGLT2阻害薬を読み解く、循環器内科医の立場から」
という演題で講演を行いました。
SGLT2阻害薬といえば、もともと“糖尿病の薬”として使われてきましたが、近年は
心臓や腎臓を守る働きが科学的に証明され、循環器内科でも非常に重要な薬の一つとなっています。
今回の講演では、このSGLT2阻害薬がどのように心臓や腎臓に良い影響を与えるのか、その多面的な作用について、最新のエビデンスを交えながらお話ししました。
ここでは、その一部を患者さんにも分かりやすくご紹介します。
🫀
1. 心臓を支える“やさしい利尿作用”
SGLT2阻害薬は、尿に糖を出すしくみにより 自然な形で水分を体の外に出す働きがあります。
これにより、
- 血液量の適正化
- 心臓への負担軽減
- むくみや息切れの改善
といった効果が期待できます。
一般的な利尿薬と比べて体への負担が少ないことも大きな特徴です。
🔋
2. 心臓のエネルギー効率を高める
SGLT2阻害薬を使うと、体が ケトン体という“効率の良いエネルギー源”を利用しやすくなることが分かっています。
同じエネルギーを作る時に
→ 心臓の消耗が少なくなる
→ ポンプ機能を保ちやすくなる
という、心臓にとって大きなメリットがあります。
🧂
3. 腎臓を守り、長く働ける状態に保つ
腎臓は血液をろ過して老廃物を出す重要な臓器です。
SGLT2阻害薬には、この“濾過フィルター”を守るための複数の作用があります。
- 糸球体の負荷をやわらげる
- 腎臓の炎症や酸化ストレスを減らす
- ナトリウム(塩分)排泄を助け、血圧も安定しやすい
これらにより 腎機能の低下を遅らせることが世界的な研究で示されています。
🔄
4. 糖尿病がなくても効果が期待できる時代へ
従来は「糖尿病の薬」として知られていましたが、現在は
- 心不全の予防
- 心臓の入院リスク低減
- 腎臓病の進行抑制
など、多くの領域で糖尿病の有無にかかわらず使われるようになっています。
これは近年の大規模臨床試験の結果によるもので、今回の講演でもこの点を多くの医師の方にお伝えしました。
🌱
まとめ — “臓器を守る薬”としてのSGLT2阻害薬
SGLT2阻害薬は、
「血糖を下げる薬」から「心臓と腎臓を守る薬」へ
という位置づけの変化が進む、非常に注目されている薬です。
患者さんにとっては、
- 心不全になりにくい
- 腎臓を長く守れる
- むくみや息切れの改善が期待できる
といったメリットがあり、当院でも積極的に治療選択肢として取り入れています。
今後も最新の医療情報を分かりやすくお届けし、
皆さまの健康をサポートできるよう努めてまいります。
